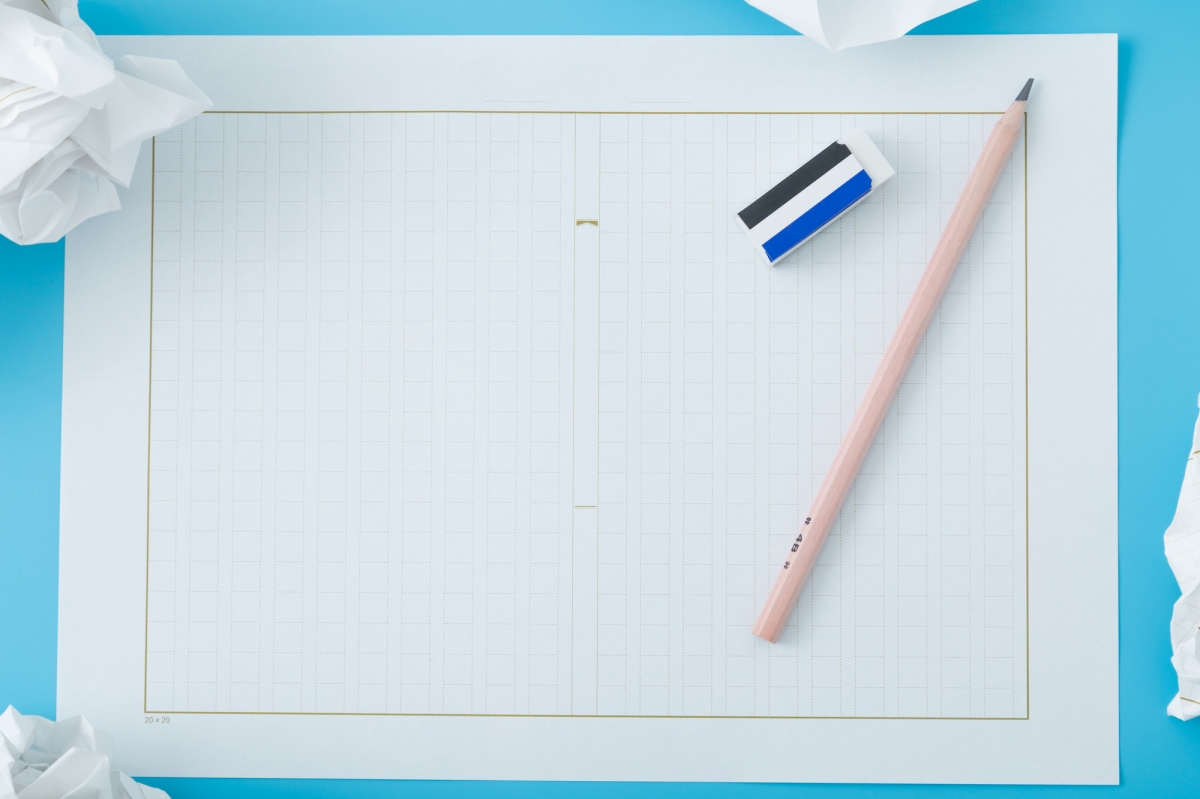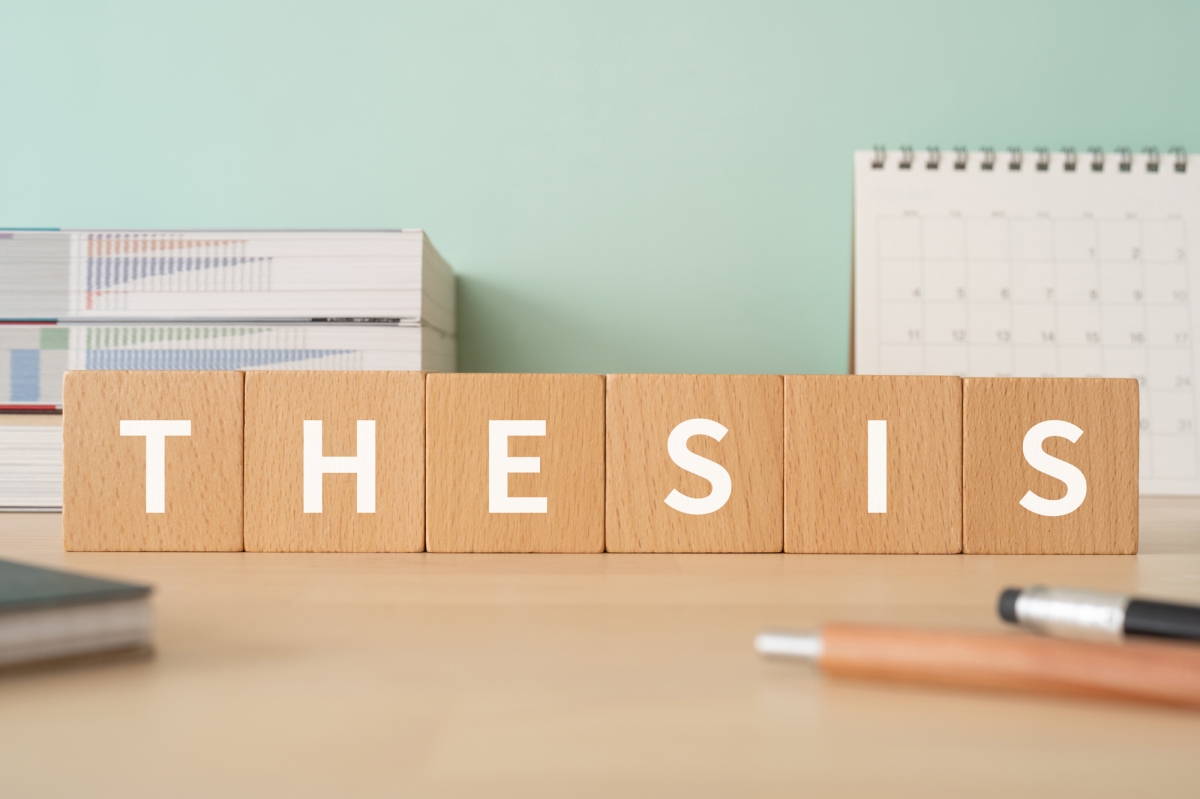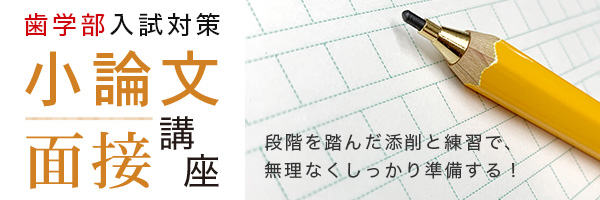医学部で小論文が出題される理由と目的とは?出題傾向や注意点まで徹底解説!
基本情報
2024/06/07(金)
(最終更新日2025/04/11)
医学部の入試では、多くの大学で小論文が課されます。それだけ小論文が重視されているからですが、事前に傾向を把握しておくのと把握しておかないのでは、結果に差が出るかもしれません。この記事では医学部で小論文が出題される理由や目的、注意点はもちろん、頻出テーマも詳しく解説しますので受験勉強の参考にしてください。
目次
1.医学部で小論文が課される理由と目的とは?
1-1.医学部に関する諸問題などが頭に入っているか
1-2.医師として必要な情報処理能力を有しているか
2.医学部小論文を突破する人と突破できない人の違いとは?
3.医学部小論文の出題傾向とは?
3-1.課題文型
3-2.テーマ型
3-3.表・グラフ読み取り型
3-4.英文型
4.医学部小論文の頻出テーマとは?
4-1.医師に求められる資質
4-2.チーム医療について
4-3.医師偏在について
4-4.総合診療医について
4-5.超高齢化社会について
4-6.救急医療について
4-7.在宅医療と看取りについて
4-8.AIと医療について
5.医学部小論文の対策方法
6.医学部小論文の対策は万全に
医学部で小論文が課される理由と目的とは?
医学部が他の学部と大きく異なる点は、将来人の命に直接関わる職業に就く可能性が高いことです。そのため医学部入試では、医師としての適性や資質を見極めるために小論文が課されています。では具体的に医師に求められる適性や素質として、どのようなポイントがチェックされているのでしょうか。以下の2点に注意してください。
医学部に関する諸問題などが頭に入っているか
医学の世界は日々進歩し、技術や設備は数十年前とは比べものにならないくらい大きく変化しました。命に関する分野だけに倫理的に問題となる部分もあり、医師としてのあり方が問われることもあります。医学部を受験するのならば、そうした問題に対して関心を持っていなければなりません。
さまざまな問題に対し、自分なりに医師としてふさわしい考え方ができるかどうかがポイントです。医学に関する問題は、将来医師となった際にも役立つ知識となるでしょう。そもそも知識が頭に入っていなければ、説得力のある小論文は書けません。まずは日頃から医学に関連する諸問題に興味を持つようにしてください。
医師として必要な情報処理能力を有しているか
医学部での教育は、将来人命に直結した仕事に就くことを前提としています。医師として仕事をするためには、表やグラフなどの資料を正確に読み解き、客観的に判断を下せる能力が必要です。小論文の試験では客観的に資料の内容を把握する力があるのか、出題者の意図を踏まえたうえで筋道を立てて自分の考えを主張できるのかなど、情報処理能力をみられています。
また臨床の現場において、医師は患者や他の医療従事者とスムーズにコミュニケーションを取るスキルが必要です。それは小論文で問われる、相手の主張をすぐに理解し、自分の意見を述べるというスキルに酷似しています。
小論文の試験は単なる学力試験では見極められない、医師としての適性や資質を測るために行われているといえます。
医学部小論文を突破する人と突破できない人の違いとは?
すべての医学部入試で小論文が課されるわけではありませんが、小論文のある医学部を受験するのであれば、きちんと小論文対策を行っておきたいところです。小論文の試験では、最近の医学に関する諸問題などが出題される傾向にあります。
小論文を突破するためには、受験勉強と平行して取り上げられそうなテーマを調べ、考える必要があります。とはいえ医療問題などは多岐にわたるため、効率的に受験勉強をしつつ、小論文対策の時間も作らなければならないのは大変です。小論文のための勉強も効率的に行うためには、予備校などを利用するのも選択肢の一つでしょう。
医学部小論文の出題傾向とは?
小論文といっても、どこも同じ形式で出題されるとは限りません。医学部の小論文では、おもに「課題文型」と「テーマ型」、「表・グラフ読み取り型」、「英文型」の形式のいずれかで出題されるのが一般的です。ただし複数の形式の中から、組み合わさって出題される場合もあります。以下の段落では、出題傾向を形式別に詳しく紹介します。
課題文型
課題文型では文字どおり課題文があらかじめ用意されており、それを読んで内容を要約させたり、個々の見解を述べさせたりします。課題文型の小論文に取り組む際、大切になるのは読解力と思考力です。
小論文を執筆するためには、まず課題文から重要なポイントをつかむ必要があります。そもそも何をテーマにしている文章なのかを理解していないと、説得力のある意見も主張できません。課題文の主張を把握し、論点を見つけることが重要です。
文章を要約するときは、過不足なく重要なポイントを含めましょう。自分の見解を述べる際は、課題文の内容や問われ方に合うよう論述する必要があります。自分なりの主張ができるようになるために、幅広いテーマに対して日頃から自分の意見を持つように心がけましょう。
テーマ型
テーマ型は提示された特定のテーマに対し、考察や解説を求める出題です。特に課題文などがなく、「○○について述べなさい」のように短いテーマだけが提示されています。論述の自由度は高いものの、テーマに関する知識があるかないかで結果に差がでやすい形式です。
取り上げられるテーマは医学に関連するものが多い傾向ですが、社会問題や時事問題など、さまざまな分野から出題される可能性があります。日頃から幅広い分野の問題に興味を持っておきましょう。
テーマ型の小論文では、単純に文章が上手に書けているだけでは点数につながりません。設問のテーマや求められていることを把握し、テーマとかけ離れた論述にならないように注意する必要もあります。
表・グラフ読み取り型
医学部の小論文では提示された表やグラフを分析したうえで、自分の考えを述べさせる表・グラフ読み取り型の形式もあります。表・グラフ読み取り型の形式では、まず与えられた表やグラフが何を表しているのか、データの傾向や特徴がどうなっているのかなどを正確に読み取る力が求められます。
表やグラフから読み取れる背景、メッセージなどを見抜き、データをもとに分析することが重要です。データが複数与えられている場合は組み合わせて考え、関連性や相違点があるのかなどを考える必要があります。分析ができたら小論文としてまとめましょう。
英文型
英文型の小論文は英語で書かれた課題文に対し、要約や意見論述を求める形式です。課題文として一定の量の英文が提示される点では、課題文型と似ています。ただし、英文型小論文の場合は課題文が英語で書かれているだけではなく、解答も英語での論述を求められるのが一般的です。そのため英語の読解力はもちろん、英作文の力もつけておかなければなりません。
課題文には医療分野はもちろん自然科学分野も含め、高度な内容の論文が取り上げられる場合もあります。英語による小論文が出題される医学部を受験する場合は、日頃から英語の題材に慣れておく必要があるでしょう。
医学部小論文の頻出テーマとは?
医学部入試の小論文でよく出題されるテーマとは、具体的にどのようなものでしょうか。医学部の小論文では医師としての資質や適性を見極めるのが目的の一つであるため、基本的には医師に必要な知識や資質・適性を問うテーマが頻出です。ここでは代表的なテーマを8つ紹介しますので、小論文対策をする上で参考にしてください。
医師に求められる資質
医師は人の命に直接関わる職業であり、社会的な責任や使命を負っています。医師を目指すならば、自覚を持って研鑽を積む姿勢が求められます。命の尊厳や患者の心情を理解し、思いやれる優しさを備えているかどうかも医師としては大切な資質です。
日々進歩する医療技術の向上、知識の習得に向上心を持って取り組める姿勢も求められます。他にも他者と協力して医療を進めていける協調性、時代によって変化していく医療倫理にも対応できる資質が必要です。最初からすべての資質を備えている人は少ないかもしれませんが、将来医師になるのを目指す学生としては意識しておきたいポイントでしょう。
チーム医療について
医療に従事しているのは医師だけではありません。特に現在の医療現場では、看護師や介護士、リハビリの専門職など複数のメディカル・スタッフが連携して一人の患者の治療にあたるチーム医療が一般的になりました。治療にあたっては患者の心理面や社会的背景にも考慮し、総合的な視点から対処することが大切です。
多様な側面から患者を捉え、治療を進めるためには、医療従事者間で互いに情報を共有するためのコミュニケーションが欠かせません。医師にも当然ながらコミュニケーション能力が必要なのはもちろん、協力体制を整えるためのリーダーシップも求められます。
医師偏在について
先進国の中でも、日本は医師の人数が少ないといわれています。医師が不足すると病院が特定の診療科に偏ったり、都市部と地方で医療格差が生まれたり、患者がたらい回しにされたりなど、さまざまな問題が生じます。また、医師不足の地では、医師自身の過重労働にもつながりかねません。最低限の医師数すら確保されていなければ、医療自体が成り立たなくなるでしょう。
医師の偏在を解消するためには、意識改革も必要です。将来医師になろうとしている学生には自分なりに医師不足をどう考えるのか、医師偏在をどう解消するのかなど、自分なりの見解を持っておくことが求められます。
総合診療医について
現代の医療現場では、特定の臓器や疾患にフォーカスした専門医が存在します。ただ専門分野が細分化すると一人の医師が対応する範囲が限られるケースもあり、患者は疾患ごとに異なる医療機関で診察を受けなければならない場合もあるでしょう。
そこで近年では幅広く多角的に診療し、家族や生活の背景も含めて対応できる総合診療医が求められるようになりました。総合診療医は性別・年齢にかかわらず、地域全体の医療を担うのも役割です。少子高齢化や地域医療・在宅医療などの課題を考えるうえでも、総合診療医としての専門性が求められています。
超高齢化社会について
日本の少子高齢化は収束する気配がなく、この先はさらに超高齢化社会になるといわれています。そのため超高齢化社会における医療問題は、今後も出題される可能性が高いでしょう。高齢者の割合が高い地域では、ますます医師不足が深刻になるかもしれません。
医療費が膨らむと、財政破綻を招く恐れもあります。在宅医療や訪問医療の需要が高まり、患者の生活の質を維持・向上させるためには、介護や福祉の分野との協力も宇重要です。小論文に取り組むにあたり、超高齢化社会の現状や医療のあり方をしっかり考えておく必要があります。
救急医療について
救急医療の専門医は、人材不足が問題になっている診療科の一つです。医師の過酷な勤務条件や医療過誤のリスクなど、救急医療の現場にはさまざまな問題があります。また本来は急を要しない軽症患者が安易に救急車を呼ぶことで、本当に救急医療を必要とする患者を受け入れられない、現場の負担が増大するなど課題も山積みです。
救急医療の現場が立ち行かなくなれば、救えるはずの命も救えません。救急医療が回らなくなっている現状や理由、どのような取り組みをすれば円滑な救急医療が行えるのかなど、具体的な提案も考えておくといいでしょう。
在宅医療と看取りについて
在宅医療は医師をはじめとした医療従事者と介護職、家族が連携し、病院やクリニック以外の自宅などで診療や治療から、ときには看取りまでを行う医療体制です。超高齢化社会が進む現代では、在宅医療が充実すれば、高齢者が家族に囲まれて余生を過ごすのも可能になります。
ターミナルケアを行う場所としても、自宅が選択肢に入ってくるでしょう。一方で在宅医療では医療や介護の専門職が常に駆けつけられるとは限らず、日々のケアは家族の大きな負担になりかねません。医師にとっても負担となる可能性があり、どのように支援していくべきなのか検討すべき内容はいろいろあります。
AIと医療について
近年AI技術が急速に発展し、X線やMRIなどの画像診断、消化器内視鏡などの検査分野を中心に医療の現場でも導入されるようになってきました。今後も活用されていくことが予想され、小論文のテーマとしても取り上げられる頻度が多くなるでしょう。
AIの活用によってデータ分析に基づいた精密な診断や、感情に左右されない最適な治療方針の決定が可能になるのは大きなメリットです。とはいえAIにはまだまだ課題もあるため、さまざまな側面から医療へ活用を考える必要があります。医療におけるAIの役割や医師としてAIの活用現場でどう働くかなど、出題意図を汲みながら論じられるようにしておきましょう。
医学部小論文の対策方法
高1生や高2生なら、部活に熱心に取り組むことも大切です。達成感やチームメイトとの友情など、人生にいい影響を及ぼす部活ならではの経験ができるため、小論文や面接の話題としても使えるでしょう。学生生活で得られる経験も、無駄にしないようにしてください。
部活動に励みながらも、医学部への進学を目指すのなら並行して医療に関連した頻出テーマの知識を幅広く、コツコツと集めておきましょう。そのテーマについて、自分なりの考えもしっかり持つようにしておくと小論文や面接対策としても有効です。
高3生になったら医学部の小論文で求められる知識のインプットを継続しつつも、アウトプットの練習も始めるようにしてください。その際、書いたものは誰かに読んでもらうようにしましょう。ただ他の勉強に差し障りがないようにする必要があるため、効率的に書き方が身につき、添削指導もしてもらえる予備校の講座を受講するのもおすすめです。
医学部小論文の対策は万全に
医師に求められる資質や適性を図るため、多くの医学部の入試では小論文が課されています。頻出テーマはいくつかありますが、受験生は他の勉強と並行しながら小論文対策も行わなければなりません。
医学部進学予備校メビオでは、医学部入試の小論文・面接対策講座を実施しています。小論文を書く上での基本的なルールや作法を、効率的に学ぶことが可能です。医学部入試の小論文対策を考えているのなら、医学部予備校メビオの小論文対策講座を検討してみてください。
医学部小論文対策ならメビオの小論文・面接講座がおすすめ!
医学部に入りたいなら、とにかくまずは1次試験に通らなくちゃ!と、ついつい後回しになりがちな小論文・面接の対策。 でも、1次試験の合格発表から2次試験までわずか2~3日しかない、という大学は珍しくありません。 最難関と言われる医学部の1次試験にせっかく合格したのに、小論文・面接の準備ができていないなんてことにならないよう、 無理なくしっかりと小論文・面接の準備を進めていきましょう。