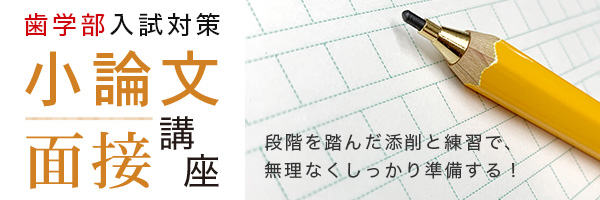医学部学士編入は難しい? メリット・デメリットや受かる人の特徴
基本情報
2021/12/28(火)
(最終更新日2025/04/11)
目次
1.医学部学士編入とは?
1-1.医学部学士編入の概要<
1-2.編入制度と一般入試との違い
1-3.選考時期は?
1-4.編入できる大学は?
2.医学部編入制度の成り立ち
2-1.医学部編入に必要な資格・条件
3.編入試験の内容は?
3-1.生命科学とは?
4.医学部学士編入を選択するメリット
4-1.受験科目が少ない
4-2.国立大学に入れる可能性がある
4-3.複数の大学を受験できる
4-4.学費を節約できる
4-5.早く目標を達成できる
4-6.社会人から医師を目指せる
5.医学部学士編入を選択するデメリット
5-1.募集定員が少ない
5-2.人間関係を再構築する必要がある
5-3.独学では難しいことがある
6.医学部編入はやめとけと言われる理由は?
7.医学部学士編入に受かる人の特徴は?
7-1.明確な目標がある
7-2.英語が得意
7-3.理系科目が得意
7-4.自己管理ができる
7-5.常に情報をチェックしている
8.医学部学士編入に受かるためのポイント
8-1.過去問対策を徹底する
8-2.計画的に行動する
8-3.医学部予備校に通う
9.医学部学士編入を目指すなら専門予備校メビオがおすすめ
医学部編入制度とは
医学部学士編入とは、他の学部から医学部へ編入するための制度です。これから試験に申し込む予定がある方は、参考にしてください。
医学部学士編入の概要
学部学士編入制度の対象者は、4年制大学を卒業した学士もしくは卒業見込みの学生です。大学によっては、4年制大学に2年以上在籍し指定の単位を取得した学生、短大や高等専門学校を卒業した人も対象となる場合があります。
医学部学士編入精度は、もともと志望していた大学を諦めて別の大学・学部に進学したものの、もう一度挑戦したいと考えている方のためにあります。医学の道に進みたいという明確な意志があり、目標達成のために努力できる方であれば合格できる可能性は十分にあるでしょう。社会人になってから医師を志したり、現役時代に進学を断念したりした方などがこの制度を活用すれば、医学部に編入することが可能になります。
編入制度と一般入試との違い
編入制度と一般入試には、以下のような違いが見られます。
| 編入制度 | 一般入試 |
|---|---|
| ・受験者数が少ない ・2年次~4年次に編入できる ・国公立大学でも共通テストは不要 ・難関大学でも一般入試より合格しやすい ・退学、留学した方でも受験できる |
・受験者が多い ・1年次から大学に在籍する ・国公立大学の場合は共通テストが必須 |
そもそも大学の編入制度の認知度は低いため、一般入試だと難しい大学でも、求められる人物像や出題傾向などを把握して対策すれば合格率は高くなります。共通テストを受ける必要がないので、仕事と勉強を両立させたい社会人にとってはありがたい制度でしょう。
選考時期は?
医学部への編入時期は2年次前期と3年次前期に分かれており、半数以上の大学が2年次前期に編入することになっています。選考時期は大学にもよりますが、国公立大学の場合は4〜7月に出願、8〜9月に一次・二次試験、9月に合格発表が行われることが一般的です。
私立大学は国公立大学よりもスタートが遅く、9〜10月に出願、10〜12月に試験、年内に合格発表が行われるという流れになっています。試験の日程は大学によって異なるため、日程が重ならなければ複数の大学の編入試験を受験することも可能です。
編入できる大学は?
2025年2月現在で27校の国公立大学で医学部編入制度を実施しています。国公立大学に比べると、私立で実施している大学は北里大学や岩手医科大学などわずかです。
また、前述の通り、ほとんどの大学が2年次編入としています。人気の名古屋大学は2022年度から2年次編入へ変更されるほか、定員もこれまでの5名から4名に縮小する方針なので注意しましょう。
なお、編入後はそれまで通っていた大学で取得した一般教養科目は単位認定されるのが一般的です。そのため、入学後すぐに医学に関する勉強に専念できるでしょう。
医学部編入制度の成り立ち
医学部の編入制度はどのような経緯で作られたのでしょうか。
<@>医学部編入制度は、1975年に大阪大学医学部が全国の医学部に先駆けて実施したのが始まりです。2000年頃には当時の文部省から、良医育成のため一度大学を卒業してから社会経験を積んだ人を積極的に医学部に編入させる方針が打ち出されました。これにより、編入制度を始める大学が一気に増加します。日本で医師を目指すためのもっともメジャーな方法は、高校卒業後すぐに医学部に入学し、医学教育を受けることです。若いうちに医学の道に進むことによって、医師として現役でいられる年数が長くなり、しっかりと経験が積める点がメリットです。
一方のアメリカでは、4年制大学を卒業した後にメディカルスクールに入学し医学教育を受けるスタイルが主流です。医師になる前に医学を始めとしてさまざまな学問を学び、人としての成熟度を高めた後に医師になれる点が特徴です。
日本の医学部編入制度はアメリカと日本のメリットをうまく融合させたシステムといえるでしょう。
※参考:21世紀の命と健康を守る医療人の育成を目指して(21世紀医学・医療懇談会第4次報告)
医学部編入に必要な資格・条件
多くの大学では、学士号を取得した方または学士号の取得見込み者を編入試験の対象者としています。中には4年制大学に2年以上在籍(見込み者を含む)して指定の単位を取得した方や、短期大学や高等専門学校を卒業した方(卒業見込み者含む)も対象にしている大学もあります。
また、医学部編入には年齢制限は設けられていないことが一般的なので、社会経験を積んだ後に医師を目指すことも可能です。
大学によっては出願の際にTOEICやTOEFLのスコアの提出を求めるなど、他に要件を設けている場合もあるため出願の際には必ず募集要項を確認しましょう。
編入試験の内容は?
医学部学士編入試験は科目がほぼ固定されており、科目も少ないため狭く深い勉強が必要です。
試験のパターンは主に次の3つに分けられます。
- 英語+生命科学
- 英語+生命科学+物理化学
- 英語+生命科学+物理化学+数学
編入試験では、大学入学共通テストは受けずに大学固有の試験のみを受けます。この他に課されるものとして志望動機書・面接・小論文もしくは課題論文があり、これらは特に重視されることもポイントです。
小論文のテーマは生命倫理や医療問題など、医療に関係する社会問題がテーマに選ばれることが多く、時事問題へ関心を持つことも必要とされます。
生命科学とは?
医学部編入試験において大変重要な科目として位置づけられている生命科学は、高校の履修科目にはありません。多くの医学部編入試験で必須科目とされているため、医学部編入試験に合格するためにはしっかりとした準備が必要とされます。
生命科学とは、高校の生物を土台として生命に関する部分をより深めたものです。中でも重要度が高いのは細胞生物学、生化学、分子生理学、生理学で、この他に遺伝学、発生生物学、免疫学など幅広い分野から出題されます。
医学部編入試験のメリットとは?
医学部学士編入制度には6つのメリットがあります。それぞれ解説するので、詳しく知りたい方はぜひ目を通してください。
受験科目が少ない
医学部学士編入制度の受験科目は英語・生命科学・理系科目が中心であり、一般入試と比べて試験対策のポイントを絞りやすいのがメリットです。
一般入試では5教科7科目の他に、志望校に合わせた個別対策も必須となります。受験科目が多いため効率よく勉強しなければならず、受験生にかかる負担は相当なものです。
編入試験の難易度も決して低くはないですが、一般入試よりは少ない科目で受験でき、必要な科目の勉強に集中できるでしょう。
国立大学に入れる可能性がある
編入試験が実施されているのは主に国立大学です。国立大学の6年間の学費は約350万円であるのに対し、私立大学の6年間の学費は安いところで約2000万、高いところでは4000万円を超えています。そのため、家計に負担がそれほどかからない国公立大学を志す方が多く、国公立大学は高倍率になりがちです。
一般入試で国公立大学を目指す場合はかなりの競争率を乗り越える必要がありますが、編入試験であれば国公立大学に入学できる可能性が出てきます。
複数の大学を受験できる
学士編入試験を受験する場合、一般の国公立大学入試と異なり日程が重複しない限りは複数の大学を受験できます。大学によって受験科目が違うため個別に対策する必要がありますが、受験できる機会が増えれば合格する確率は上がると考えられます。
一般の国公立大学入試はどの大学も試験日が同じなので、前期と後期でそれぞれ1校しか受けられません。受験生にとっては大きなプレッシャーとなるでしょう。
学費を節約できる
先述のように、医学部学士編入制度は主に国公立大学において導入されています。
国公立大学の医学部に学士編入した場合、年間の授業料の相場は約54万円です。一人暮らしをするなら生活費120万円(一月当たり10万円とする)が加わるものの、合計で174万円ほどに抑えられます。
もし私立大学の医学部に6年間通った場合、年間で約333万円(総額で約2,000万円)の学費が必要です。どの大学を選ぶか、どの地域に住むかによる違いはありますが、生活費も考慮すると経済的な負担は少なくないでしょう。
早く目標を達成できる
医学部に学士編入すると在籍日数が少なくなり、6年かからずに医師免許を取得できる可能性があります。仮に3年次から編入したとすると、1〜2年次で必修とされる教養課程の講義を受ける必要はありません。
医学部に通う年数を短縮できれば、勉強期間のみならず学費も節約できます。特に私立大学の医学部だと数年の違いで金額に差が生じるため、金銭的な負担を少しでも減らしたいなら学士編入で医師を目指すメリットは大きいでしょう。
社会人から医師を目指せる
医学部学士編入制度は、社会人が医師を目指す「第二のチャンス」です。基本的に年齢制限はなく、40代・50代・60代で試験に合格するケースもあります。
医師になるきっかけはさまざまで、社会人になってから医学の道を志す方も珍しくありません。中には学生時代は医学と無縁でも、けがや大病を経験して医師になる方もいます。
年齢を重ねていても努力次第で医学部への編入は可能なので、本気で医師になりたいなら挑戦する価値はあるでしょう。
医学部学士編入を選択するデメリット
ここまで医学部学士編入制度のメリットを紹介しましたが、デメリットも存在します。良い面と気になる点を比較して受験するか決めましょう。
募集定員が少ない
医学部学士編入制度のデメリットとして、募集定員の少なさが挙げられます。一般的には各大学で数名程度しか募集しないため、競争率が高くなるのは避けられません。
一般入試の場合、100人以上の新入生を募集することもあります。その時点で必要な人数は確保できているため、編入試験ではごくわずかな人数しか合格できないのが現実です。限られた枠を通過するには、ペーパーテストだけでなく面接や小論文の対策もしっかり行う必要があります。
人間関係を再構築する必要がある
医学部に限らず、年次の途中から編入して人間関係の壁にぶつかるのはよくある悩みです。自分以外はみな顔見知りという環境にあえて飛び込むため、積極的に交友関係を築く努力が求められます。
医学部に在籍していて知り合いがいないと、情報共有の面で課題に直面します。例えば、定期テストの過去問や実習の準備など、単位を取得するために必須の情報を得られず苦労するのです。医学部で学ぶには学業以外の努力も必要だと知っておきましょう。
独学では難しいことがある
医学部学士編入制度の情報を独自に入手するのは難しく、独学で合格を目指すのは至難の業です。そのため予備校で体系的なカリキュラムに沿って勉強するのが近道でしょう。
予備校には最新のものも含めて受験に関連する情報が蓄積されています。試験情報や学習方法などのデータは編入試験の受験に欠かせないため、専門の予備校で対策すべきです。
医学部への編入を検討しているなら、医学部進学予備校の「メビオ」がおすすめです。まずは説明会や無料体験会に参加してみてはいかがでしょうか。
医学部編入はやめとけと言われる理由は?
中には医学部編入に対してネガティブな意見もあります。その理由は以下の3つです。
- 実際に勉強したら思っていた学問とは違った
- 編入後に勉強についていくのが辛い
- 将来の選択肢が狭まる
念願の医学部に編入したものの、勉強してみたら期待していた内容ではなかったと感じる方もいます。特に文系出身者ほどギャップが大きいかもしれません。
また医学部のカリキュラムは厳しく、短期間で多くの知識を習得しなければならない編入生はプレッシャーを感じる可能性もあります。
医学部に編入した時点では医師になるつもりでも、気持ちが変わることもあるでしょう。しかし進路変更は難しく、卒業後のキャリア選択で後悔するかもしれません。
確かに大変な側面もありますが、医師になりたい理由を明確にすれば目標達成に向けて努力できるでしょう。
医学部学士編入に受かる人の特徴は?
医学部学士編入で狭き門を突破できる方には、5つの特徴があります。ここではそれぞれ解説します。
明確な目標がある
医学部に編入してまで医師になりたい方には明確な目標があり、強い気持ちを持っています。あえて違う環境に飛び込むのは勇気がいることで、漠然とした憧れがあるだけでは不十分です。もし途中で挫折しそうになっても、明確な目標があれば厳しい勉強を乗り越える活力になるでしょう。
編入試験には面接があり、医師になりたい理由を口頭で述べる必要があります。ペーパーテストだけでは試験を突破できないため、面接に向けて大学が求める人材像を把握しておかなければなりません。時間をかけて準備すれば、本番でも志望理由を伝えやすくなります。
英語が得意
医学部学士編入試験では、多くの大学で英語が必須の科目とされています。一般入試より英語の配点比率が高いため、文系・理系を問わず英語が得意な方に有利でしょう。
大学によってはTOEFL・TOEICの結果を編入試験に反映できるケースがあります。いずれのスコアも取得時から2年間は有効とされるため、編入試験の日程に合わせて受験するのも一つの手段です。
ただし医学部ならではの出題傾向として、専門用語を含む論文から出題されることも珍しくありません。いわゆる「医学部英語」の知識を問う大学もあるので、英語が得意でも油断は禁物です。
理系科目が得意
文系出身でも理系科目が得意な方は、医学部への編入が可能です。生命科学を筆頭に、数学・科学・物理などの基礎知識を理解して応用問題まで対応できるよう対策しましょう。
学生時代に理系科目が苦手だった方は、編入試験に備えてしっかり学ぶ必要があります。難問は少ないため、きちんと基礎を押さえれば合格率が高まります。
独学が困難な場合は、医学部受験に特化した専門予備校で指導を受けるのがおすすめです。結果として費用や時間の節約につながり、短期間で合格水準に近づけるかもしれません。
自己管理ができる
医学部の編入試験で合格するには、自己管理のスキルが問われます。現役の大学生なら通っている学校の勉強と同時進行で受験対策をしなければならず、限られた時間をやりくりする必要があります。社会人は仕事との両立になるため、学生以上にハードなスケジュールになるでしょう。
当初は意欲が高くても、モチベーションを保てず苦戦する方は少なくありません。自己管理に課題を感じているなら、同じ志を持つ仲間がいる予備校に通うと中だるみを防げます。学ぶ環境を変えれば勉強に集中しやすくなるかもしれません。
常に情報をチェックしている
試験で合格するのに学力が必要なのはもちろんですが、情報も同じくらい重要です。医学部の編入試験を実施する大学は30校ほどあり、受験資格や受験科目はそれぞれ異なります。同じ大学でも、年度によって条件が変わるケースもあります。
従って勉強と並行して情報収集をしている方は、合格しやすいといえるでしょう。面接や小論文の出題傾向などを把握しないと対策を立てにくいため、志望校が決まったら定期的に調べることを推奨します。スケジュールの一部にリサーチの時間を組み込むと、無理なく情報を得られます。
医学部学士編入に受かるためのポイント
医学部学士編入で合格するには、要点を押さえて効率よく勉強しなければなりません。ここでは3つのポイントを紹介します。
過去問対策を徹底する
医学部の編入試験と一口にまとめても、出題傾向や科目には違いがあります。過去問の対策を入念に行い、大学ごとのクセを知ることが合格への近道です。
必ずしも過去問の傾向通りになるとは限りませんが、直近数年間の問題を一通り解いておけば問題の流れをつかめます。どの大学でも生命科学は重要科目とされており、重点的に学習しましょう。
編入試験の枠は狭く、1点や2点の差が合否を左右するかもしれません。もし苦手科目があれば、平均点を取れる程度になるよう対策することが大切です。確実に点を取れるように勉強してください。
計画的に行動する
自己管理と通じる部分がありますが、計画的な行動の積み重ねが合格への近道となります。学生も社会人も忙しいのは同じなので、タイムマネジメントを徹底しましょう。
社会人は時間のやりくりが難しいため、空き時間をうまく活用して勉強のスケジュールを立てるよう心掛けてください。時には残業や休日出勤などもあると想定されることから、余裕を持たせるのが大切です。
また試験で実力を発揮するには、万全の状態で臨む必要があります。体調管理にも気を配り、本番までにやるべきことを終わらせるようにしましょう。
医学部予備校に通う
医学部の編入試験は難易度が高いため、予備校に通うことで効率よく学習を進められます。在籍している講師は医学部受験の情報に精通しており、独学では難しい面接・小論文などの対策で疑問点があっても質問できるのは心強いでしょう。
もちろん費用はかかるものの、それに見合うサービスを提供してくれます。学習環境を整えるための投資と捉え、予備校に通うのも選択肢の一つです。自宅では勉強に集中できない、講師のアドバイスがほしいような場面で予備校が役立つのではないでしょうか。
医学部学士編入を目指すなら専門予備校メビオがおすすめ
医学部学士編入を目指すなら、実績豊富な専門予備校メビオがおすすめです。生命科学や英語などの重要科目はもちろん、面接や小論文の対策まで万全のサポート体制を整えています。
独学では難しい最新の試験情報も随時提供され、講師陣は医学部受験に精通したベテランぞろい。一人ひとりの習熟度に合わせた丁寧な指導で、限られた時間で効率的に実力を伸ばせます。
まずは説明会や無料体験授業にご参加ください。メビオは全力で合格への道のりをサポートいたします。